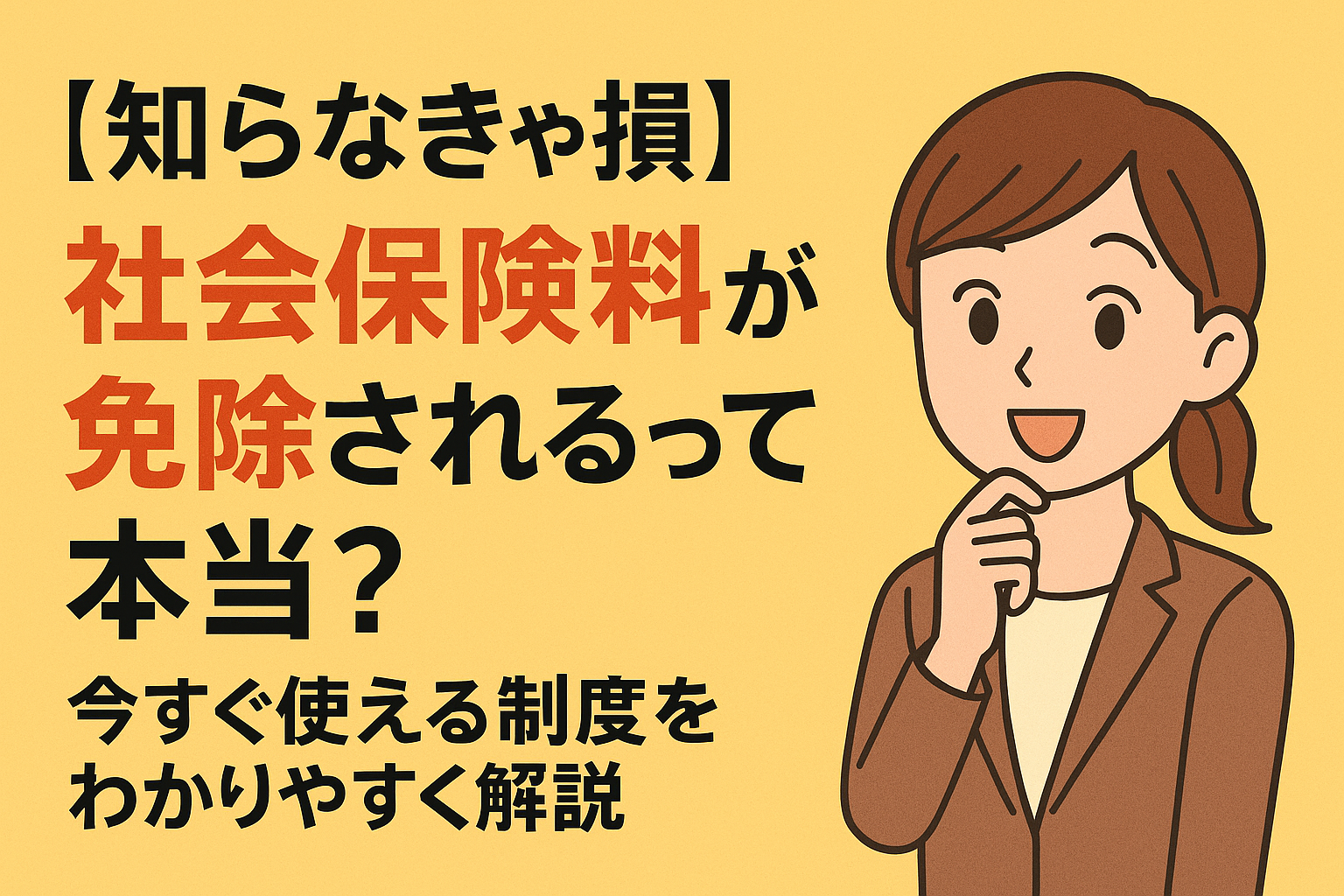この記事は、「福祉の支援を探しているけど、どこから調べればいいか分からない…」という方に向けて、自分自身の経験や調査結果をもとに書いています。私自身も申請のハードルに悩んだ一人だからこそ、分かりやすくまとめたいと思いました。
働きながら、子育てや生活を支えるのは本当に大変ですよね。
その中でもじわじわ重くのしかかるのが【社会保険料】。
でも実は!
ある条件を満たすと、社会保険料が免除される制度があるんです!
この記事では、2025年時点での最新ルールをもとに、初心者にもわかりやすく「社会保険料免除制度」の仕組みと活用方法をまとめました!
【社会保険料免除制度を始めるきっかけ】に、ぜひ活用してくださいね!
社会保険料免除制度とは?
社会保険料免除制度とは、特定の条件に当てはまった人が、健康保険料や厚生年金保険料の支払いを免除される仕組みです。
これを知っているだけで、毎月の負担がぐっと軽くなるかも!
対象となるのは主にこの2パターンです。
- 育児休業・産休取得中の人
- 失業・低所得で収入が少ない人
【1】育児休業・産休における社会保険料免除
基本ルール(2022年10月改正後)
- 月末時点で育児休業中であること
- 休業が連続14日以上あること
(分割取得でも合計14日以上ならOK!)
【具体例】
- 4月30日〜5月13日(14日間連続育休)
➡︎ 4月・5月ともに免除対象!
産後パパ育休(2025年改正)
- 子の出生後8週間以内に取得する「産後パパ育休」も対象!
- 14日以上の休業があれば、連続でなくてもOK
- ただし賞与月だけは1か月以上連続の休業が必要
注意ポイント
- 育休中に有給休暇を挟んでも大丈夫!
- 分割取得でも、1か月内で14日以上あれば免除対象!
【2】雇用保険料免除(64歳以上の方向け)
- 4月1日時点で64歳以上の労働者は、雇用保険料が免除されます!
- ただし、労災保険料は支払い対象なので注意!
- 65歳以上で新しく働き始めた場合は対象外です。
【3】国民年金保険料の免除・納付猶予
もし仕事をしていない、または収入がかなり低いなら、国民年金保険料の免除や納付猶予も選択肢に!
所得別・免除早見表(扶養1人の場合)
| 免除区分 | 年収目安 |
|---|---|
| 全額免除 | 102万円以下 |
| 3/4免除 | 88万円+扶養控除 |
| 半額免除 | 128万円+扶養控除 |
| 1/4免除 | 168万円+扶養控除 |
さらに、20歳〜50歳未満であれば、所得が低い人は納付猶予制度も利用可能!
また、失業した場合は、前年所得を問わずに「特例免除」が使えます。
【4】健康保険料の減免(市区町村制度)
住んでいる自治体によっては、健康保険料の減免制度もあります!
例えば東京都品川区では独自基準を設けて減免支援をしています。
- 基準:世帯所得が自治体基準以下
- 手続き:市区町村窓口で申請
- 必要書類:課税証明書、預金通帳など
✅お住まいの市区町村役所に相談してみましょう!
手続き・申請先まとめ
| 制度区分 | 申請先 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 育休免除 | 会社(事業主経由) | 育児休業証明書など |
| 国民年金免除 | 年金事務所 | 所得証明書、失業証明書 |
| 健康保険減免 | 市区町村 | 課税証明書、預金通帳など |
【2025年版】最新改正まとめ
- 産後パパ育休:14日以上の取得で免除OK!(連続不要)
- 育休分割取得:2週間単位でも対象に!
- 64歳以上:雇用保険料免除。ただし労災保険は対象外!
免除制度をうまく使うコツ!
【社会保険料免除制度を始めるきっかけ】は、
まず「自分が対象になるかどうか」を調べること!
育児休業中なら会社の総務部に、
無職・失業中なら年金事務所や市役所に相談して、
早めに申請手続きを進めましょう!
初心者におすすめの参考サイト
まとめ
社会保険料の免除制度を知っているかどうかで、
これからの生活負担が大きく変わるかもしれません。
「知らなきゃ損!」と思える今このタイミングで、
【社会保険料免除制度を始めるきっかけ】に、ぜひ役立ててくださいね🌟