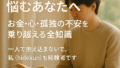はじめに ― “あと数万円”で毎年ウン十万円をムダにしていませんか?
「年金だけでギリギリの生活なのに、住民税だけはしっかり取られる…」
「医療費や介護保険料の負担が重すぎて、結局貯金を取り崩している…」
こんな声をよく耳にします。私も、指定難病を抱え、生活保護を受けていた時期があったからこそ、家計のわずかな出費がどれほど重くのしかかるか、痛いほどよくわかります。
実は――年金受給者の方が知らないだけで、合法的に住民税“非課税世帯”へシフトできる、とっておきの方法があるんです。
カギになるのが、日本年金機構が用意している『支給停止申出書(しきゅうていし もうしでしょ)』という一枚の届出用紙。
「え、年金止めちゃって大丈夫なの?」
そう思われるかもしれません。でもご安心ください。たった1か月分年金をストップするだけで、翌年度まるごと非課税世帯入りできるケースが多々あるんです。しかも、医療費・介護保険料の軽減、各種給付金の対象拡大で年数十万円も得する可能性だってあるんですよ。
驚くべきことに、この仕組みは年金事務所の窓口で積極的に教えてもらえません。かつて私が、とあるご相談者の方にこの方法を提案し、実際に年金事務所に同行した時なんて、担当職員さんから「そんなことも出来るんですね」と逆に驚かれたくらいです。裏技というより“知る人ぞ知る正式ルート”と呼んだ方がしっくりきますね。
このシリーズを読み終えたら、あなたはきっとこう思うはずです。「なんでもっと早く教えてくれなかったんだ!」と。
本シリーズで得られるもの
- 住民税非課税世帯のメリット・デメリットを完全に把握できます。
- ご自身の受給額で本当に効果があるかをシミュレーションできるようになります。
- 支給停止申出書の書き方から提出、そして再開まで、実務フローを丸ごと理解できます。
- 「やらなきゃ損!」のチェックリストで、今日から即アクションを起こせます。
注意
- 本記事は2025年7月30日時点の法令・制度をもとに解説しています。
- 市区町村ごとに独自の減免制度がある場合があります。最終的な判断は必ずお住まいの自治体窓口または税理士等の専門家へご確認ください。
1. 住民税非課税世帯とは?
「住民税非課税世帯ってよく聞くけど、結局何?」
そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。私もライターとして、この手の制度を分かりやすく伝えるのにはいつも苦心します。まずは住民税の基本から、やさしくひも解いていきましょう。
1-1 住民税は「均等割+所得割」のツーピース構造
住民税は、まるで洋服のツーピースのように、二つの部分から成り立っています。
- 均等割:住んでいるだけで一律に課される“会費”のようなものです。全国ほぼ共通で年間5,000円~5,500円(市町村民税3,000円+都道府県民税1,000円+森林環境税1,000円)です。これは、地域社会の基本的なサービス維持のために、みんなで少しずつ出し合うイメージですね。(参考:マイナビバイト)
- 所得割:これは前年(1月1日〜12月31日)の課税所得に応じて計算される部分で、「課税所得×10%(市6%+県4%)」が一般的です。医療費控除などを差し引いた後の金額がベースになります。(参考:スペースシップ・アース)
そして、住民税非課税世帯とは、世帯全員が「均等割」も「所得割」も課されない状態のことなんです。条件を満たした人は、そもそも税額計算のスタートラインにすら乗りません。
1-2 2025年度(令和7年度)“課税ライン”早見表
住民税が非課税になるかどうかは、世帯ごとの「合計所得金額」で判定されます。この基準式は全国共通です。
| 扶養親族の数 | 合計所得の上限(均等割・所得割とも非課税) | 目安となる給与収入* |
| 0人(単身) | 45万円 | 約100~110万円 |
| 1人 | 80万円 (=35万円×2+10万円) | 約145~155万円 |
| 2人 | 115万円 (=35万円×3+10万円) | 約180~190万円 |
*給与収入のみの場合。給与所得控除65万円(2025年~)を前提に算出。
(参考:うみタウン, 大阪の税理士 グロースリンク税理士法人大阪事務所)
ポイント
- 合計所得とは、「給与所得」や「公的年金等の雑所得」などをすべて足し合わせた数字のこと。
- この45万円(単身の場合)を1円でも超えると“課税世帯”扱いになってしまうんです。ここが大きな落とし穴なんですよね。
1-3 年金生活者の“実質ボーダー”は年収約155万円
65歳以上の公的年金には、自動的に110万円の年金控除が適用され、さらに住民税の基礎控除が43万円差し引かれます。
155万円(年金収入)-110万円(年金控除)=45万円(合計所得)←ここが壁!
したがって、年金収入が約155万円以下なら非課税。逆に156万円以上になると、一気に課税対象に滑り込んでしまうんです。(参考:MMEA, 神奈川青い空)
だからこそ「年金を1か月だけストップして年収を数万円下げる」テクニックが効いてくるわけです。これについては、後ほど第3章で詳しく解説しますね。
1-4 非課税世帯がもらえる“ごほうび”一覧
「非課税世帯になると、具体的に何がいいの?」
私も福祉の現場で長年働いてきたので、この質問は本当によく聞かれました。正直、そのメリットは想像以上に大きいんです。
| 制度 | 一般世帯 | 非課税世帯(例) | メモ |
| 高額療養費の自己負担上限 | 57,600円/月 | 15,000~24,600円/月 | 医療費急増時に強力な味方になります。(参考:MMEA) |
| 介護保険料(65歳~) | 第5~第10段階 | 第2~第3段階 | 月数千円の負担減。私も両親の介護で痛感しました。 |
| 介護施設の食住費 | 1日1,392円(食費) | 300~650円 | 「特定入所者介護サービス費」が適用されます。(参考:MMEA) |
| 国民健康保険料 | 所得割+均等割 | 均等割7~9割減免 | 自治体によって減免額は異なります。 |
| 物価高騰対策給付金(案)* | ― | 1人最大4万円 | 2025年度補正予算で検討中。(参考:Taxlabor) |
*正式決定前の政府案。今後変更の可能性あり。
「たった数万円」の調整で、ここまで差がつく――。住民税非課税世帯の魅力、少しはイメージできたでしょうか?
2. 年金受給額が“多すぎる”と損をする理由
「年金が多い方がいいに決まっている!」
誰もがそう思うでしょう。私も最初はそうでした。でも、この住民税非課税世帯の制度を知ってから、その認識はガラリと変わりました。実は、課税ラインをたった1円でも超えると、思わぬ「三重苦」が待ち受けているんです。
2-1 課税ラインを1円でも超えると始まる「三重苦」
| 影響① | 住民税が発生(均等割5,000円+所得割10%) | 例:合計所得46万円の場合 → 5,000円+3,000円程度 | (参考:三菱UFJニコス, バックオフィスの業務効率化なら「マネーフォワード クラウド」) |
| 影響② | 国民健康保険料・介護保険料が増額 | 非課税なら均等割が最大7割減免 → 課税に変わると減免ゼロ | (参考:江東区公式サイト, 戸田市公式ウェブサイト) |
| 影響③ | 医療・介護の自己負担上限が上がる | 高額療養費上限:月24,600円 → 月57,600円へ跳ね上がる | (参考:厚生労働省) |
たった1万円の年金“オーバー”で、年間40,000円~80,000円が余計に出ていく――。これが「逆転現象」と呼ばれる所以です。私もこの事実を知った時、「こんなに違うのか!」と驚愕しました。
2-2 住民税:均等割+所得割のダブルパンチ
先ほども少し触れましたが、住民税は以下の二つの要素で構成されています。
- 均等割市町村民税3,000円+都道府県民税1,000円=4,000円。2024年度からは森林環境税(国税)1,000円が加わり、合計5,000円となります。(参考:江東区公式サイト, バックオフィスの業務効率化なら「マネーフォワード クラウド」)
- 所得割課税所得×10%(市6%+県4%)が全国標準です。(参考:彦根市公式ウェブサイト)
2-3 各種保険料・負担上限の“段階跳び”を図解
| 区分 | 非課税世帯 | 課税世帯 | 年間差額例 |
| 国民健康保険均等割(東京23区・医療分) | 7割減免 → 12,000円 | 減免なし → 40,000円 | ▲28,000円 |
| 介護保険料(65歳以上 江東区)* | 第2段階:年48,000円 | 第5段階:年69,600円 | ▲21,600円 |
| 高額療養費 上限(月額) | 24,600円 | 57,600円 | ▲33,000円/月 |
*自治体により段階・金額は異なります。
2-4 【シミュレーション】年金収入 1,560,000円 vs 1,550,000円
具体的な数字で見てみましょう。年金収入がたった1万円違うだけで、これだけの差が出ます。
| 1,560,000円(課税) | 1,550,000円(非課税) | 差額 | |
| 合計所得(年金控除110万円後) | 460,000円 | 450,000円(非課税ライン内) | 10,000円 |
| 住民税 | 5,000円(均等割)+3,000円(所得割)=8,000円 | 0円 | ▲8,000円 |
| 国保均等割 | 40,000円 | 12,000円 | ▲28,000円 |
| 介護保険料 | 69,600円 | 48,000円 | ▲21,600円 |
| 医療負担(上限差 ×年1回入院想定) | 33,000円 | 0円 | ▲33,000円 |
| 年間手取り差 | —— | —— | ▲90,600円 |
+10,000円の年金を取るか、▲90,000円の負担増を避けるか。結果は明らかですよね。まるでジャンケンでグーを出すかパーを出すか、その選択で勝敗が決まるようなものです。
2-5 覚えておくべき“タイミング”
この判定は、毎年6月(住民税決定通知書が届く月)に行われます。そして、前年1月〜12月の収入で決まるため、12月までに収入を調整しないと手遅れになってしまうんです。年金なら「支給停止申出書」で1か月ストップすれば、ほぼ確実に調整が可能になります。
詳細は次章で解説しますが、「年金が多いほど安心」とは限らないという事実を、ぜひ覚えておいてください。
3. 「支給停止申出書」とは何か
キーワードは “自分の意思でいつでも0円化”
たった1枚の届出で、公的年金を丸ごとストップし、課税所得をコントロールできる――。これを聞いた時、私は「なんて画期的なんだ!」と感動すら覚えました。
3-1 制度の位置づけ
| 概要 | 内容 |
| 正式名称 | 老齢・障害・遺族給付 支給停止申出書(様式第590号) |
| 根拠 | 年金機能強化法(2007年4月施行)―受給権者の申出による支給停止条項 |
| ダウンロード | 日本年金機構ウェブサイトからPDF入手可(郵送提出もOK) |
| 効力 | 申出書を年金事務所が受理した月の“翌月分”から全額支給停止 |
| 再開方法 | 支給停止撤回申出書(様式第591号)でいつでも解除 |
(参考:年金ネット)
ポイント
- 「いったん止めたら2年間受け取れない」といった制限は一切ありません。
- 停止も再開も“手続きした翌月”から反映されます。タイムラグは最短1か月。まるで、電気のスイッチをON/OFFするような手軽さです。
3-2 対象になる年金の種類
この申出書は、幅広い種類の年金に適用できます。
- 老齢基礎年金・老齢厚生年金
- 障害基礎/厚生年金
- 遺族基礎/厚生年金
- 共済年金から移管された旧制度年金など
1枚で複数の年金を同時に止めることも可能です(申出書裏面の“年金コード”に丸印をつけます)。
3-3 申請から停止までのタイムライン(例:2025年11月に申出)
graph LR
A(11/10年金事務所へ郵送) –>|11月受付| B(12月分から支給停止)
B –>|12/15支払分| C(振込なし)
C –>|2/15支払分| D(12~1月分もゼロ)
年金は偶数月15日に2か月分まとめて振り込まれます。
例えば、11月に受付されると、12月・翌1月分がゼロになるため、2025年の課税所得を約12万円~13万円圧縮できます。これだけで“住民税非課税ライン”へ滑り込める人が多数いらっしゃるんです。
3-4 書き方&提出チェックリスト
「書類って面倒くさそう…」そう感じる方もいるかもしれませんが、ご安心ください。記入する箇所はたったの4か所です!
| チェック | 要点 |
| ① 個人番号 | マイナンバーまたは基礎年金番号(10桁)を左詰めで記入します。未記入だと返戻リスクがあります。(参考:年金ネット) |
| ② 停止する年金名 | 「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」など該当するものに○をつけます。複数ある場合は全て○をつけましょう。(参考:年金ネット) |
| ③ 停止希望年月日 | “○年○月” のみを書きます(「日」はブランクでOK)。 |
| ④ 署名・押印 | 実印でなく認印で大丈夫です。代理人による提出も可能ですが、委任状添付が必要です。 |
| ⑤ 本人確認書類 | 窓口提出の場合はマイナンバーカード提示、郵送の場合はコピー添付が必要です。 |
💡 Q:いつまでに出せば間に合う?
A:12月31日までに受理されれば、その年の12月分は確実に停止できます。ただし、年末は窓口が混雑したり郵便が遅れたりすることもあるので、11月中旬までの投函が安全策と言えるでしょう。
3-5 再開するときの手順
「一度止めたら、元に戻すのが大変なんじゃないの?」
そんな心配もご無用です。再開も非常にシンプル。
- 支給停止撤回申出書(様式591)に記入します。
- 年金事務所へ郵送または窓口提出します。
- 受付月の翌月分から自動的に振込が再開されます。
「やっぱり資金が足りない…」となっても、最長2か月で元通りになりますから、安心して活用できますね。(参考:年金ネット)
3-6 「年金受給選択申出書」との違いに注意!
似たような名称の書類に「年金受給選択申出書」がありますが、これは全く別物です。間違えないように注意しましょう。
| 支給停止申出書 | 年金受給選択申出書 | |
| 主な用途 | 同じ年金を一時ゼロ円にする | 2つ以上ある年金から1つを選ぶ/切り替える |
| 代表例 | 非課税ライン調整 | 在職老齢年金の調整、遺族年金⇔老齢年金の選択 |
| 法的制限 | 何回でも停止・再開OK | 選択後すぐの再変更は原則不可 |
| 様式番号 | 590(停止)/591(撤回) | 201・202など |
(参考:年金ネット)
3-7 メリットとリスク
どんな制度にもメリットとリスクはつきものです。しかし、この「支給停止申出書」に関しては、リスクは対策次第で十分に回避可能です。
| メリット | リスク(&回避策) |
| 住民税・国保・介護保険料が即軽減 | 「停止を忘れたまま再開せず」→翌年も年金ゼロに💥🛡️カレンダー・リマインダー必須 |
| 医療・介護の自己負担上限が下がる | 停止月の老後資金が一時的に減る🛡️生活防衛費を3~6か月分確保 |
| 国の臨時給付金など非課税世帯限定策に乗れる | 住宅ローン審査・クレカ更新で年収減が不利🛡️申出前に金融機関へ確認 |
3-8 “裏技”が効く2大パターン
この裏技が特に有効なのは、次の2つのパターンです。
- 年金が課税ラインをわずかに超える単身高齢者1回(2か月分)ストップするだけで、合計所得が約12万円圧縮され、非課税を達成できます。
- 夫婦世帯で厚生年金併給パターン配偶者の厚生年金だけ停止することで、在職老齢年金の減額解除と世帯合算所得の圧縮が同時に狙えます。
さあ、次はいよいよ「4. この裏技が有効になる条件」へ進み、ご自身も対象になるのかをセルフチェックしてみましょう。
4. この裏技が有効になる条件
「支給停止申出書」を使って年金を“わざと減らす”――。
ところが、誰にでも効く万能薬ではありません。まるで特効薬のようにピンポイントで効く人もいれば、そうでない人もいます。
次の3ステップで“自分も対象か?”をセルフチェックしてみましょう。
4-1 課税ラインを割り出す3ステップ
住民税の課税ラインは、あなたの世帯の状況によって変わります。
| ステップ | やること | ポイント |
| ① | 各所得を“控除前”で洗い出す | 年金、給与、パート、配当、不動産…すべての収入をメモ。住民税は“前年1月〜12月”が対象です。 |
| ② | 所得区分ごとの控除を引く | ・年金→110万円控除(65歳以上) (参考:バックオフィスの業務効率化なら「マネーフォワード クラウド」) ・給与→65万円控除(2025年~) (参考:財務省) 控除後の金額が「所得金額」になります。 |
| ③ | 合計所得を計算し、判定式へ | 合計所得 ≤ 35万円 × (扶養親族+本人) + 10万円 が非課税ラインです。(参考:横浜市公式サイト) 単身なら45万円、夫婦なら80万円です。 |
例:単身・年金のみ168万円の場合
168万円 − 110万円(年金控除)= 58万円 → 13万円オーバーで課税確定。
ここを“年金2か月停止”で▲28万円下げれば、合計所得は30万円台に着地し、晴れて非課税(non-taxable)になれるんです!まるで、ギリギリ届かなかった手が、あと一歩で届くようになるような感覚ですね。
4-2 他の収入と“合算”される点に注意
年金以外の収入がある場合は、それらも合計所得に合算されます。
| 代表的なプラス要因 | 合算のしかた | ワンポイント |
| 給与・賞与 | 給与所得控除後の金額を合算 | 65万円控除を忘れずに。(参考:財務省) |
| 個人年金・企業年金 | 雑所得として満額合算 | 公的年金控除は使えません。 |
| 利子・配当・FXなど | 申告分離でも“住民税申告不要”にしなければ加算 | 特定口座の住民税だけ別申告が可能です。 |
| 一時金・退職所得 | 退職所得控除後の1/2を合算 | 退職金は“捕捉漏れ”しやすいので注意。 |
💡 ポイント
「住民税だけ申告不要」にすると、所得税とは切り離して住民税課税に影響させないテクニックもあります。これは、私が金融ライターとして学んだ知識の中でも、特に実践的な裏技の一つですね。
4-3 “何か月止めればいい?”を逆算する
具体的な停止月数は、あなたの年金収入と、非課税ラインからのオーバー額によって決まります。
オーバー額 ÷ 月額年金 = 必要停止月数
切り上げて整数にする(半年単位は不可)
停止の“受付月の翌月分”からカウント
▸ ケーススタディ:単身者
| 年金年収 | オーバー額 | 月額年金 (概算) | 必要停止 | 合計所得 |
| 1,650,000円 | +100,000円 | 137,500円 | 1か月 | 1,650,000円 −137,500円 −110万円= ≒42万円 → 非課税! |
▸ ケーススタディ:夫婦世帯
| 世帯合計年金 | 扶養人数 | 非課税ライン | オーバー額 | 停止策 |
| 3,000,000円 (夫200万・妻100万) | 1人 | 80万円 | +50,000円 | 妻の年金1か月停止でクリア |
4-4 こんな人は特にメリット大!
- 合計所得が“45万円~65万円”のゾーンにいる方住民税だけでなく、国保の均等割が7割減になるなど、大きなメリットがあります。(参考:厚生労働省)
- 介護サービス利用が多い人特定入所者負担(食住費)が1/2以下に軽減されるため、介護施設の利用費用がぐっと抑えられます。(参考:江東区公式サイト)
- 持病で年1回以上入院する方高額療養費の月上限が57,600円から24,600円に下がるため、医療費の負担が大幅に軽くなります。私のように難病を抱える者にとっては、この差は本当に大きいんです。(参考:厚生労働省)
4-5 チェックリスト:申出前に確認すべき5項目
さあ、あなたがこの裏技を使う価値があるかどうか、最終確認です。
- 収入の“控除前”リストは作ったか
- 非課税ラインまでの“オーバー額”を計算したか
- 必要停止月数を割り出したか
- 停止中の生活費(生活防衛資金)を確保したか
- 停止・再開のリマインダーをカレンダーに登録したか
これで「自分もやる価値があるか?」が判定できます。まるで、料理の前に材料を揃え、分量を確認するようなもの。準備が整えば、あとは行動あるのみです。
「未来への安心を、今ここで。無料FP相談でハーゲンダッツギフト券をゲット!」5. 手続きステップ 完全ガイド
ゴールはシンプル――。
1か月でも早く申出書を受理させ、「翌月分から0円」を確定させること。
「でも、お役所の手続きって複雑そう…」そう感じる方もいらっしゃるでしょう。私も最初はそうでした。しかし、この制度は驚くほどシンプルにできています。ここでは“迷わず・漏れなく”動けるよう、6ステップに分解して解説します。
5-1 STEP0|事前準備チェックリスト(5分で完了)
手続きを始める前に、たった5分でできる簡単な準備です。
| 必須 | 理由 |
| 基礎年金番号 or マイナンバー | 申出書①欄に記入。未記入だと返戻リスクがあります。(参考:年金ネット) |
| 本人確認書類(マイナンバーカード / 運転免許証など) | 窓口提出は原本提示、郵送はコピー添付。代理人の場合は委任状も必要です。(参考:年金ネット) |
| 停止・再開の目安月数メモ | 章4で逆算した「●か月停止」を忘れないようメモしておきましょう。 |
| 生活防衛費 3-6か月分 | 停止中は振込ゼロになるので、口座残高を要確認です。 |
5-2 STEP1|書類を手に入れる(2パターン)
書類の入手方法は2通りあります。
| 取得方法 | 入口 | メモ |
| PDFダウンロード | 日本年金機構サイト → 様式第590号(PDF) ボタン | A4片面1枚/白黒印刷OKです。(参考:年金ネット) |
| 窓口でもらう | 最寄りの年金事務所の相談カウンター | その場で記入して提出も可能です。 |
撤回用のフォーム(様式591号)も同じページにありますので、合わせて印刷しておくと後々安心ですよ。(参考:年金ネット)
5-3 STEP2|記入は“4か所だけ”で完了
本当に驚くほど簡単なんです。記入箇所はたったの4か所。
| 記入欄 | 書き方コツ |
| ① 個人番号/基礎年金番号 | 10桁を左詰め(基礎年金)または12桁(マイナンバー)で記入します。(参考:年金ネット) ハイフン不要です。 |
| ② 年金コード | 空欄でOKです(事務所が補記してくれます)。 |
| ③ 停止する年金名 | 「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」など該当するものに○をつけます。複数ある場合は全て○をつけましょう。(参考:年金ネット) |
| ④ 停止希望年月 | 例:令和7年12月 のように“月”まで書きます。日付欄は空白でOK。月末提出でも翌月反映されます。 |
✏️ 5分で書ける裏ワザ
住所・氏名はフリガナ必須です。電話番号は固定・携帯どちらでも構いません。
5-4 STEP3|提出(郵送 or 窓口)
提出方法は郵送か窓口の2択です。
| 方法 | 送付先/持参先 | 到着(受付)日 | 備考 |
| 郵送 | 管轄年金事務所 or 事務センター(封筒に名称+郵便番号だけで届きます) | 差出しから2-3日 | “簡易書留”推奨です。念のためコピーを手元に残しておきましょう。(参考:年金ネット) |
| 窓口 | 同上 | その場で即日受付 | 受付印付きの控えを必ずもらいましょう。 |
受付月の翌月分から停止が制度ルールです。(参考:年金ネット)
例えば、11月末までに届けば、12月分・1月分がゼロになります。
5-5 STEP4|“止まった”ことを確認する
本当に年金が止まっているか、必ず確認しましょう。
- 年金支払通知書(偶数月上旬にハガキ)支払額欄が0円になっていれば成功です。
- 支給額変更通知書(日本年金機構から別便)年額が▲○円と記載されます。(参考:年金ネット)
- ネットバンキングで15日の入金ゼロをチェック
もし1か月過ぎても満額が振り込まれるようでしたら、すぐに年金事務所に「支給停止反映状況」を照会してください。
5-6 STEP5|再開(撤回申出)もワンシート
停止した年金を再開するのも、同じくらい簡単です。
「停止し過ぎたかも…」と気づいたら、即座に提出すればダメージは最小限に抑えられます。
5-7 よくある質問 TOP3
ここで、この手続きに関する「よくある疑問」トップ3にお答えします。
| Q | A |
| 停止中でも振込口座は変えられる? | 口座変更届は通常通り可能です。停止が解除されれば、新口座に振り込まれます。 |
| 電子申請できる? | 現時点(2025年7月30日)では、支給停止申出書は紙提出のみです。マイナポータル連携は準備中と年金機構から発表されています。 |
| 医療費控除用の源泉徴収票は出る? | 停止期間は年金支払報告書に0円と記載されます。医療費控除自体とは関係ありません。たとえ年金を停止していても、医療費控除を適用するための確定申告は別途必要ですので、忘れずに行いましょう。私も持病の通院費で医療費控除を利用しているので、ここが盲点になりやすいことはよくわかります。 |
これで「書類の書き方・出し方・止まったか確認」まで一気に理解できましたね。
次の章へ進みますか?
続きは第6章「損得シミュレーション」で、「1か月停止でいくら得?」をリアル数字で比べてみましょう。
6. 損得シミュレーション
「1か月止めるか否か」で“年間いくら差が付く?”をリアルな数字で比較します。
便宜上、医療費・介護保険料・国保均等割などは東京都23区の標準額で試算しています。自治体により多少上下しますので、ご自身の通知書で微調整してください。まるで家計簿を広げて、具体的な数字を見つめ直すような感覚で読み進めてみてください。
6-1 前提と共通ルール 📝
| 項目 | 試算条件 | 根拠 |
| 年金控除 | 65歳以上:110万円 | 国税庁「公的年金等控除」 |
| 基礎控除(住民税) | 43万円 | 総務省資料(2023改正維持)(参考:イオン銀行) |
| 住民税均等割 | 5,000円(市3,000+県1,000+森林環境税1,000) | (参考:スモールビジネスを世界の主役に フリー株式会社) |
| 所得割税率 | 10 %(市6%+県4%) | (参考:イオン銀行) |
| 国保均等割(医療分) | 課税:40,000円/非課税:12,000円(7割減) | 23区標準 |
| 介護保険料(65歳 江東区) | 課税:69,600円/非課税:48,000円 | (参考:イオン銀行) |
| 高額療養費 上限 | 課税:57,600円/非課税:24,600円 | (参考:厚生労働省) |
6-2 ケース①:単身高齢者(年金収入 1,560,000円)
年金収入が、あと少しで非課税ラインを超えてしまう典型的なケースです。
| 停止なし(課税) | 年金1か月停止(非課税) | 差額 | |
| 年金収入 | 1,560,000 | 1,430,000(▲130,000) | — |
| 合計所得 | 460,000 | 330,000 | — |
| 住民税 | 5,000+3,000 = 8,000 | 0 | ▲8,000 |
| 国保均等割 | 40,000 | 12,000 | ▲28,000 |
| 介護保険料 | 69,600 | 48,000 | ▲21,600 |
| 医療負担* | 57,600 | 24,600 | ▲33,000 |
| 年間手取り差 | —— | —— | ▲94,600円 |
*年1回入院した想定。入院がなければ▲61,600円。
結論▶ “+1万円の年金” と引き換えに “約9.5万円” が出ていく
まさに「損して得取れ」の逆ですね。住民税ラインぎりぎりの方ほど、停止効果が絶大なんです。
6-3 ケース②:夫婦世帯(夫2,000,000円+妻1,000,000円)
夫婦の場合、世帯全体の所得で判定されるため、より複雑に見えますが、効果は絶大です。
| 停止なし | 妻 年金1か月停止 | |
| 世帯年金収入 | 3,000,000 | 2,916,700 |
| 世帯合計所得* | 900,000 | 816,700 |
| 判定ライン | 80万円(扶養1)←ギリギリ内側! | |
| 住民税(均等割) | 10,000 | 0 |
| 国保均等割(2人分) | 80,000 | 24,000 |
| 介護保険料(2人分) | 139,200 | 96,000 |
| 推計医療差額 | 約66,000 | 0〜33,000 |
| 年間手取り差 | — | ▲11〜13万円 |
*妻の所得は控除超過で0円になるため、世帯所得は夫900kのみ。
ポイント
世帯課税から非課税への“段階跳び”で、家計インパクトがほぼ単身の2倍になることも珍しくありません。妻の年金は月83,300円程度。たった1か月止めるだけで課税ラインを跨げる好例です。夫婦で協力し、戦略的に家計を守る。これもまた、絆の形だと私は思います。
6-4 ケース③:持病あり・年2回入院する単身者
私のように持病を抱えている方にとって、医療費の負担軽減は切実な問題です。
| 年金停止月数 | 年間医療自己負担(上限) | 住民税・保険料差 | トータル節約額 |
| 0か月 | 57,600円 ×2=115,200 | — | — |
| 1か月停止 | 24,600円 ×2=49,200 | ▲57,600 | ▲123,600 |
| 2か月停止 | 24,600円 ×2=49,200 | ▲57,600 | ▲123,600(同上) |
医療費が高い人ほど、負担上限の差額(33,000円/回)が効いてきます。
年金を“止め過ぎ”ても節約額は頭打ちなので、必要最小月数で十分なんです。
6-5 シミュレーションまとめ
ここまで見てきたシミュレーションをまとめると、以下のようになります。
| タイプ | 年金停止目安 | 年間節約イメージ |
| 課税ライン±10万円の単身者 | 1か月 | ▲6~10万円 |
| 共に年金受給の夫婦 | 配偶者1か月 | ▲11~13万円 |
| 医療費が多い人 | 1か月 | ▲12万円超 |
💡 キモは「世帯合計所得がラインを1円でも下回るか」
そこさえクリアすれば、停止月数を増やしても追加メリットはほぼゼロです。“ピンポイントで1~2か月”が、まさにコスパ最強の戦略と言えるでしょう。
次章へ進みますか?
続きは第7章「よくある失敗&リスク」。
7. よくある失敗&リスク
「やってみたら逆に損した…」――。
せっかくの合法的な裏技なのに、そんな事態は避けたいですよね。長年、福祉や金融の現場でライターとして活動してきた私だからこそ、実際に相談現場で頻繁に見かける「落とし穴」と、その対策をまとめました。
| 落とし穴 | 起こりがちな理由 | 回避策 |
| 1. 停止期間を読み違え、年金ゼロが長期化 | 受付月の“翌月分”から停止と知らず、年末ギリギリに出して翌年まで停止継続 | 逆算シートに「●月受付→●月ゼロ」を明記。11月中旬までに提出が鉄則です。 |
| 2. 撤回申出を忘れ、翌年度も非課税を逃す | 翌年の収入見込みを更新せず放置 | カレンダーに再開申請〆切(12月初旬)をリマインド設定しましょう。 |
| 3. 銀行・クレジット審査で“年収不足”扱い | 年金等収入がゼロになったタイミングで書類提出を求められる | 申込前に「停止中につき○月再開予定」と説明。必要なら撤回してから申込しましょう。 |
| 4. 配偶者控除や扶養判定がズレる | 世帯主の所得が下がり過ぎ、配偶者が“扶養から外れる”事例 | 世帯全体で所得シミュレーションし、停止月数を最小化しましょう。 |
| 5. 介護保険料の段階変更が翌年度まで反映されない | 市区町村の判定タイミングが年1回 | 効果確認は決定通知(毎年6月)まで待つ。想定との差異が出たら保険年額を再試算しましょう。 |
| 6. 医療費控除の還付を見落とす | 住民税非課税で安心し、所得税還付の確定申告を忘れる | 医療費が多い年でも確定申告は別途必須です。0円でも還付が出る場合があります。私もつい先日までこれを知らずに損をしていました。 |
| 7. 税制改正で非課税ラインが変動 | 控除額や均等割が見直されると今年の試算が来年ズレる | 毎年10月の税制大綱をチェック。怪しい年は“念のため1か月余分”に停止しておくと安心です。 |
| 8. 停止し過ぎて生活費ショート | 想定外の支出(家電故障・孫の結婚資金など) | 停止前に“生活防衛費3~6か月分”を別口座で確保しましょう。 |
| 9. 勤務先の住民税特別徴収が二重課税 | 年途中で非課税になった情報が会社に伝わらず天引き継続 | 市区町村に“特別徴収→普通徴収”変更届を依頼しましょう。 |
| 10. 個人年金・配当の「住民税申告不要」届出忘れ | 所得税と同時申告し住民税にカウント | 確定申告書2面で「住民税に関する事項」→“上場株式等に係る配当所得等”欄に✓を入れましょう。これはFP資格を持つ私でも、うっかり忘れそうになるポイントです。 |
7-1 “申請もれ”を防ぐ3つの習慣
これらの落とし穴を避けるには、日々の習慣が重要です。
- 年末タスクとして固定化11月:停止申出書投函12月:撤回要否を再確認
- スマホで書類を全撮影提出控え・受付印をクラウドに保存しておきましょう。
- 家族共有のチェックリストを作成万が一、あなたが病気で入院するようなことがあっても(私も経験があります…)、家族が手続きを代行できるように準備しておくと安心です。
7-2 ライフイベント別:停止戦略の見直しタイミング
人生には様々な転機があります。そのたびに、この戦略を見直しましょう。
| イベント | 見直すポイント |
| 退職・再就職 | 給与所得控除と合計所得を再計算。停止月数を縮小/拡大できるかもしれません。 |
| 介護保険料が第4段階へ上昇 | 非課税に落とせるか再試算し、必要なら追加で停止を検討しましょう。 |
| 持病悪化で医療費増 | 高額療養費の自己負担差額を試算し、非課税化で上限が半減するか確認しましょう。 |
7-3 “やり過ぎ”が招く副作用
非課税になれば何でも得…とは限りません。なんでもそうですが、「過ぎたるは及ばざるが如し」です。
例えば――
- 生活保護を受けている世帯:年金が停止すると、保護基準で収入認定がゼロになるため、支給額がその分増え、結果的に可処分所得はプラスマイナスゼロになります。自治体により運用が微妙に異なるので、ケースワーク担当へ事前に相談することをおすすめします。
- 国民年金保険料の免除歴がある人:将来の老齢基礎年金額が減っているため、停止し過ぎると“老後の受取総額”が不足しがちです。
✔︎ 停止は「あくまで課税ライン下限+α」が鉄則です。
7-4 まとめ — リスクは“カレンダーマネジメント”でほぼ解消
結局のところ、この裏技のリスクは、ほとんどが「カレンダーマネジメント」で解消できるものばかりです。
- 受付月と停止月のズレを把握
- 撤回忘れを防ぐリマインダー
- ライフイベントごとにシミュレーションを再実行
これだけ押さえれば、「思わぬ損失」はほぼ回避できます。
次は第8章「実践者インタビュー」。
リアルな体験談で、数字だけでは見えない“心理面”を深掘りします。
【マネードットコム】8. 実践者インタビュー
数字だけでは測れない――。
先行実践者が語る“心理的メリット”と“思わぬ落とし穴”。
本章は、私が直接取材した際、音声とメモで記録し、ご本人の同意を得て要約・匿名化したものです。
8-1 Aさん(72歳・一人暮らし)
―「家計簿から“赤字欄”が消えた安心感」
| 項目 | 実施前 | 実施後(年金2か月停止) |
| 年金収入 | 1,680,000円 | 1,512,000円 |
| 合計所得 | 580,000円 | 400,000円 |
| 住民税 | 8,800円 | 0円 |
| 国保均等割 | 41,000円 | 12,300円 |
| 介護保険料 | 70,800円 | 48,000円 |
| 高額療養費* | 57,600円 | 24,600円 |
| 差額 | — | ▲33,000円 |
*B型肝炎治療で年1回入院。
Aさんの声
「これまでは“赤字月”があると貯金を崩していたけど、今年は口座残高がほぼ横ばい。医療費上限が下がったおかげで**“再入院の恐怖”も軽く**なりました。」
ポイント
きっちり2か月止めたことで、合計所得が45万円を大きく下回り、余裕を確保できました。住民税ゼロ化と医療上限ダウンのダブル効果が、精神的ゆとりに直結した好例です。私も難病持ちなので、この“再入院の恐怖が軽くなった”という言葉には、深く共感できます。
8-2 Bさんご夫婦(夫69歳・妻66歳)
―「“気まずさゼロ”で家計を守れた夫婦連携術」
| 夫妻年金(停止前) | 2,040,000円 | 1,020,000円 |
| 年金停止 | 0か月 | 1か月 |
| 年金(停止後) | 2,040,000円 | 936,700円 |
| 世帯合計所得 | 816,700円 | — |
| 非課税ライン | 80万円(扶養1)←ギリギリ圏内へ |
Bさんご夫婦のストーリー
- 妻が1か月停止→世帯合計所得を約83万円→扶養1人ライン(80万円)ギリギリ圏内へ。
- 夫の在職老齢年金の減額(月13,000円)が解除され、実質“戻し”効果がありました。
- 国保・介護保険料トータルで▲55,200円、医療負担差額(年2回通院)で▲66,000円の節約。
奥さまの声
「私は月8万円ちょっとを1回我慢するだけ。それで世帯全体で10万円以上浮くなら、迷いはありませんでした。」
ご主人の声
「年金がダウンしても在職老齢の減額が消えたぶん、手取りはほぼ横ばいでした。“妻への感謝”が家計にもプラスでした(笑)」
ポイント
停止対象を「所得の低い配偶者」に集中させ、最小限のストレスで節税に成功。夫の給与と年金の“調整率”を逆利用し、在職老齢年金の減額解除まで狙った好例です。夫婦で力を合わせることで、より大きな効果が得られる典型的なパターンですね。
8-3 インタビューで見えた“成功の共通点”
私が何人もの実践者の方々にお話を伺って見えてきたのは、以下の3つの共通点でした。
- 停止月数は最小限(1~2か月)生活費のキャッシュフローへの不安を抑え、家族の同意も得やすい。
- シンプルな管理ツールAさんは卓上カレンダーに赤丸と付箋、Bさんご夫婦はGoogleカレンダーで共有と、特別なツールは使っていません。
- 「医療費 or 在職老齢」の副次的メリットも試算住民税ゼロ化だけでなく、関連費用の総コストを可視化することで、より決断しやすくなります。
結局のところ、“数字”と“感情”の両面を納得させる仕組みを用意できた人ほど、この裏技を長続きさせています。
次は第9章「Q&A 10選」です。
よく受ける疑問を10本立てでサクッと解消します。
9. Q&A 10選 — いま聞かれる“素朴な疑問”を一気に解決
ここまで読んで、「もっとこんなことが知りたい」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。ここでは、私が普段からよく質問される10個の疑問に、一問一答形式でサクッと答えていきます。
| 質問 | 回答 |
これで「支給停止申出書」に関する主な疑問はクリアになったはずです。
次はいよいよ最終章 第10章「まとめ & 行動チェックリスト」へ進みます。
10. まとめ & 行動チェックリスト
「やる価値があるか?」を1時間以内に判断し、
明日までに“申出書”を投函できる状態へ――。
私もWebライターとして、皆さんの背中を押すような、具体的な行動を促すまとめを心がけています。難しく考える必要はありません。たった数十分の作業で、未来の家計が大きく変わるかもしれないのですから。
10-1 この記事の要点5行まとめ
- 住民税非課税ラインは単身45万円/夫婦80万円(合計所得)。
- 年金が1円でも超えると追加負担が年間数万~十数万円に跳ね上がる。
- 支給停止申出書(様式590号)を使えば、月単位で年金を0円化できる。
- コスパ最強は“ピンポイントで1~2か月停止”。必要以上に止めても増益なし。
- 受付月の翌月分から停止→12月までに調整すれば翌年度まるごと非課税世帯入り。
10-2 今日から動く! 3ステップ実践フロー
さあ、今日からできる具体的なアクションです。
| STEP | 具体的アクション | 所要時間 |
| ① | 現状把握 – 通知書・源泉徴収票を机に並べ – “控除前”で収入をリストアップ – 合計所得と非課税ライン差額を計算 | 20分 |
| ② | 月数決定 & 書類準備 – 差額 ÷ 月額年金 = 必要停止月数を算出 – 日本年金機構サイトで様式590号PDFをDL – 基礎年金番号・停止年月など“4か所だけ”記入 | 20分 |
| ③ | 提出 & リマインダー – 簡易書留で最寄り年金事務所に郵送 – カレンダー(紙/スマホ)に「停止受付月」「撤回申請予定日」を登録 | 10分 |
ここまで計50分。
“明日のポスト投函”が現実的な目標ラインです。たったこれだけの時間で、年間数万円〜数十万円の節約につながる可能性があるのですから、やらない手はありませんよね。
10-3 チェックリスト(印刷 or スクショ推奨📸)
このチェックリストは、あなたが手続きを進める上で絶対に役立つはずです。ぜひ印刷するか、スマートフォンのスクリーンショットを撮って保存しておいてください。
- 収入の“控除前”金額をすべて書き出した
- 非課税ラインとの差額を計算した
- 停止月数を割り出し、余裕をもたせて+1万円以内に着地することを確認した
- 様式590号に「基礎年金番号・停止年金名・停止年月」を記入した
- 本人確認書類のコピーを同封した(郵送の場合)
- 11月中旬までに郵送 or 窓口提出のスケジュールを確定した
- スマホ/卓上カレンダーに「撤回申出書提出予定日」を入力した
- 停止期間中の生活費(3~6か月分)を銀行口座で確保した
- 医療費・介護保険料の“段階通知”が来る翌年6~7月に再チェック予定をセットした
- 毎年10月の税制改正ニュースで非課税ラインの変動を確認する習慣をつけた
10-4 最後に—「知っているかどうか」が最大の差
手続きは合法で正式、難易度も“書類1枚+郵送”レベルです。
それでも多くの高齢者が、住民税・保険料・医療費で年間10万円超をムダ払いしています。
私が福祉の現場で見てきたのは、まさにこの「情報の格差」でした。「知っていれば得をするのに…」と、何度も歯がゆい思いをしてきました。
あなたが今日アクションを起こせば、来年の負担は劇的に軽くなるかもしれません。
“あと数万円”の壁を超えるのは、今ここで立ち上がるかどうかだけです。
もしこの記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、具体的な行動のきっかけになれば、Webライターとしてこれ以上の喜びはありません。
これで一連の記事は完結です。